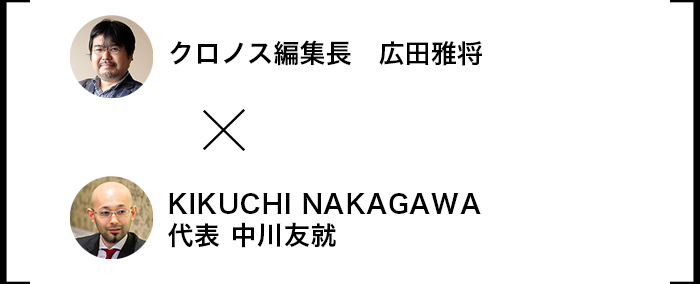
クロノス編集長 広田雅将氏と共に、時計の魅力やこだわりを熱く語っていただくことでご好評を得ている、歯車バトン対談。
昨年末はその特別編として、独立時計メーカー『KIKUCHI NAKAGAWA』の中川友就氏をゲストにお招きして、“いい時計の条件”について語り合っていただきました。
今回初めて開催した公開形式の歯車バトンは、当選されたご出席者も気軽に参加できるカジュアルなスタイルで進行しました。
参加者からは、「実際に時計を見ながらお話を聞くとより納得ができた」、「聞きたかったことを直接質問できていい時間になった」「お二人の話を直接聞けたことが何より嬉しかった」という声をいただきました。
独立時計メーカー『KIKUCHI NAKAGAWA』とは?
日本は、GPSソーラーなどの独自の先進技術や、伝統的なマニュファクチュールの技術も擁する時計生産先進国である。そして大手メーカーばかりでなく、新進の独立系ブランドも多く誕生している。KIKUCHI NAKAGAWAもそのひとつ。パリで時計作りを学んだ後、現地で時計修理の実績を重ねた菊池悠介と、刀匠修業から時計師に転向し、シチズン時計勤務や小規模時計製造のプロセスを経験した中川友就というふたりの時計師が昨年立ち上げた。そのデビュー作となるMURAKUMOは、王道スタイルである小径の2針+スモールセコンドに、ブレゲ数字やスペード針といったスイス時計の伝統に則った意匠をちりばめる。こうした先人へのリスペクトに加え、ブランドの個性を主張するのがケースや針に施された“磨き”だ。現代の匠と呼べる手仕事により、類い稀な美しさが際立つ。クラシックかつモダン。日本ならではの美的感性と熟練の技が生んだ注目作だ。

第1回「“いい時計の条件”4つのポイントとは?」

広田:まず中川さんはどうして独立時計メーカーになろうと思ったんでしょう。最近は、優れた独立時計師、あるいはKnottなど面白いメーカーも色々出てきていますが。
中川:それほどこだわりがなくて。独立時計師でもメーカーでも、どちらにしても時計を作ることに変わりはないですからね。でもとにかくいいものを作ろうというのは大前提にありました。
広田: Murakumoの計画はいつぐらいに始まったんですか。

中川:昨年1月に前の会社を辞め、そこから4月ぐらいまでにデザインを決めて、試作を始めました。会社が立ち上がったのが6月で、8月末には完成していました。
広田:さて今日の本題ですが、中川さんにとって何がいい時計の条件だと思いますか。
中川:デザインと設計、仕上げ。そして付随する価値みたいもの、ブランド性や歴史、希少性だったり。大きくはその4つだと思うんです。そのすべてが平均的に高いものは当然いい時計ですが、どこか欠けていても飛び抜けているものがあれば、好きになる要素がすごく強い。そういう時計がいい時計じゃないかなと最近思うようになっています。
広田:パテック フィリップはよくできているし、あとはロレックスも。
中川:F.P.ジュルヌとか。
広田:パッケージングがいいという点ではどんなものがありますか。
中川:やはりF.P.ジュルヌ。オーデマ ピゲのロイヤル オーク、A.ランゲ&ゾーネのランゲ1とか。ロレックスなんかもかなりいいですね。
広田:オメガもいいですよ。平均点高いです。あとグランドセイコーとかシャネル、ルイ・ヴィトンですね。

中川:そうした有名ブランドに対して、独立時計師の時計は平均点の高さよりは、どこか癖が強くて、その面白さを楽しむところがあると思います。だから我々もMurakumoを作る上で、特徴を作るということから、デザインや仕上げ、外装を含めた設計という目に見える3つの要素をすごく意識しました。
広田:そこなんですよ。Murakumo は“鬼磨き”と言われるほどの仕上げについて言われますが、その前提であるパッケージングについて中川さんに伺いたかったんです。
中川:やはり大切なのはデザイン、設計、仕上げ。パッケージングを考える上で特にこの3つは大事かなという気がします。
広田:ある意味では、今の時計はトータルバランスに優れ、はずれがなくなったと言えそうですね。80年代や90年代ぐらいの時計って、わりに緩かったりするじゃないですか。
中川:全体の出来がすべて緩かったので、その中でデザインが際立ち、差別化されたことで、この時計は良い悪いと評価されたと思いますね。
広田:あのガタガタの中でバランスがとれていたから良かったですね。
中川:出来が悪いなりにも、デザインの部分ではちゃんと差別化しているわけですよ。今と比べたらケースの出来は全然悪いし。それでも良さがあるというのはパッケージングが優れていたからでしょう。

広田:ところでMurakumoはどのような工程で作られるのですか?
中川:ブランクはNCの機械で削り出してもらい、まず最初にやるのは紙やすり。1200番ぐらいからひたすら切削面を消していく。1200から始めて2000番、2500番、3000番、5000番、それから最後に7000番まで上げます。
広田:7000番ってすごいですね。
中川:そこから今度はダイヤモンドペーストを綿棒につけて手で磨くこともあるし、リューターを使って磨くこともある。最初は1ミクロンで、一旦トレシーで拭って、最終的に0.5ミクロンで仕上げる。でも傷が逆に見えてくることもあるので、その場合は7000番ぐらいに戻ることもあります。
広田:ケースをポリッシュする場合、通常バフを当てて表面仕上げをするわけじゃないですか。何故研磨剤で磨くという古典的な手法を選んだんですか。
中川:立ち上げたばかりのメーカーなので、設備投資の資金がなかったから(笑)。
広田:結果としてバフを使わないことによって、面はダレにくくなりますね。でも下地の整形を紙やすりでやっていくと角が落ちそうですけど、落ちていない。

中川:そうですね。これが腕の見せ所で。そこが下手だといくら磨いても、光りはするけど、こんなに綺麗に面は出ないですね。感覚は指先で掴んでいますね。それはもう訓練うんぬんじゃなくて、センスの問題。できるやつはできるし、できないやつはできない。
広田:刀鍛冶の経験や審美眼は、今の時計作りに活かされていますか。
中川:磨き自体は研ぎ師の仕事なので。ほとんど役に立ってません(笑)。ただモノの良し悪しを見るという意味では、美術品も時計も割と近く、まず全体の姿が良くないと駄目だというのがありますね。そのあとに個々を見ていく。そういう経験は、この時計では無意識に取り入れている気がします。
広田:あくまでも全体のパッケージングがまずありき。その上で卓越した仕上げをアイコン化するために入れた。でも正直、傷つきが気になって困るレベルですよ。
中川:デザインを決める時に、菊池さんに頼んだのがアイコン化できること。それはデザインの差別化も含まれていますが、まずは見たことがないものにすること。その上でどんな仕上げにしようかという話になった時に、菊池さんからは全面ポリッシュがいいと即答ですよ(笑)。買った人に「これどうしよう、綺麗すぎて着けられないよ」と迷わせるぐらいのものを作りたかった。でも生まれ出たものはいつか滅びるし、その過程を楽しむのが一番いいんじゃないかな。どうしても気になるなら、もう1本買えばいいじゃないですか(笑)。
広田:うわ、ビジネスやってる(笑)。
構成・文 柴田 充
今回の対談に関してのご意見・ご質問をお待ちしております。ぜひコメント欄からご投稿ください。


広田 雅将
Masayuki Hirota
時計ジャーナリスト・時計専門誌『Chronos日本版』編集長
1974年大阪府生まれ。会社員を経て、時計専門誌クロノス日本版編集長。国内外の時計賞で審査員を務める。監修に『100万円以上の腕時計を買う男ってバカなの?』『続・100万円以上の腕時計を買う男ってバカなの?』(東京カレンダー刊)が、共著に『ジャパン・メイド トゥールビヨン』(日刊工業新聞刊)『アイコニックピースの肖像 名機30』などがある。時計界では“博士”の愛称で親しまれており、時計に関する知識は業界でもトップクラス。英国時計学会会員。

中川 友就
Tomonari Nakagawa
ウオッチメーカー「KIKUCHI NAKAGAWA」代表
刀匠での修行の後に時計師へと転向する。時計専門学校卒業後、フランスでの修行を経てシチズン時計株式会社に就職。腕時計の設計、製造、調整など大規模製造業務に一通り従事。その後、東京時計精密株式会社へ転職し、独立時計師の小規模な製造現場に携わる。退社後、菊池悠介氏と共に、KIKUCHI NAKAGAWAを立ち上げて、現在に至る。






